各
![]() に対し、
に対し、
![]() となる正数
となる正数 ![]() ,
, ![]() を取れば、
定理 6.2 により、
を取れば、
定理 6.2 により、
また、![]() を十分小さくして、
を十分小さくして、
![]() であるとすれば、
であるとすれば、
![]() が 0 でない範囲では
が 0 でない範囲では
![]() となるので、
となるので、
(7.98)
なお、逆にこれが成り立たなければ、
近似解はたとえ収束したとしてもそれは解ではないことを意味し、
すなわち「近似解」が近似になっていないことになる。
その意味で、(7.1) (またはその部分列) が 0 に収束することは、
近似解がちゃんと解を近似しているかどうかを示すことにもなるので、
この ![]() の評価は 誤差評価 と呼ばれる。
ただし、「誤差」とは言っても、
実際に真の解との差を意味するわけではなく、
あくまで解の弱形式 (2.2) の意味での誤差であるから、
この値が小さいからといって近似解が真の解に近い状態であるとは限らない。
の評価は 誤差評価 と呼ばれる。
ただし、「誤差」とは言っても、
実際に真の解との差を意味するわけではなく、
あくまで解の弱形式 (2.2) の意味での誤差であるから、
この値が小さいからといって近似解が真の解に近い状態であるとは限らない。
3.2 節で説明したように、
Glimm の差分においては無限個の確率変数の組
![]() が意味を持ち、
これをランダムに取ることによってこの近似解が弱解に近づき、
よってこの誤差
が意味を持ち、
これをランダムに取ることによってこの近似解が弱解に近づき、
よってこの誤差 ![]() が 0 に近づくことが期待される。
その意味で、
が 0 に近づくことが期待される。
その意味で、![]() は
は
また、6 節で考えた部分列や極限
(定理 6.2) では
![]() のことを考慮してはいなかったから、
各
のことを考慮してはいなかったから、
各 ![]() 毎に近似解を収束させる列や極限が取れたことになり、
つまりそれらの列や極限も
毎に近似解を収束させる列や極限が取れたことになり、
つまりそれらの列や極限も ![]() に依存していることになる。
この節では、さらにその極限が弱解となるような
「適切な」
に依存していることになる。
この節では、さらにその極限が弱解となるような
「適切な」![]() を取れることを示すことが目標となる。
を取れることを示すことが目標となる。
まず、この ![]() を変形する。
を変形する。
![]() は、
は、![]() 上、及び Riemann 問題の波のつなぎ目
(衝撃波や接触不連続の波の上、あるいは膨張波の端) を除いては滑らかで
方程式 (1.1) を満たす。よって
上、及び Riemann 問題の波のつなぎ目
(衝撃波や接触不連続の波の上、あるいは膨張波の端) を除いては滑らかで
方程式 (1.1) を満たす。よって
今、この (7.5) の右辺の和の各項を ![]() と書くことにする:
と書くことにする:
![$\displaystyle E_n(\Delta x,\theta,\phi)
=
\int_R\phi(t_n,x)\left[U^\Delta\right]^{t=t_n-0}_{t=t_n+0}dx,
%\label{eq:error:E_n}
$](img652.gif) |
(7.103) | |||
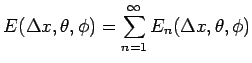 |
(7.104) |
[Glimm], [Smoller] では、![]() を一旦階段関数で近似してから、
それに対する
を一旦階段関数で近似してから、
それに対する ![]() の
の ![]() に関する直交性を示して、
そこからその近似に関する評価を行っているが、
ここでは [Dafermos] に従ってそのままの
に関する直交性を示して、
そこからその近似に関する評価を行っているが、
ここでは [Dafermos] に従ってそのままの
![]() に対して誤差評価を行う方法で
話を進めることにする。
に対して誤差評価を行う方法で
話を進めることにする。
![]() は、直接これが 0 に収束することを
示すことができるわけではなく、
確率変数
は、直接これが 0 に収束することを
示すことができるわけではなく、
確率変数 ![]() に関する平均が 0 に収束することを
示すことができるのみである。
よってそれを示すために、まずこの
に関する平均が 0 に収束することを
示すことができるのみである。
よってそれを示すために、まずこの ![]() の「
の「![]() に関する積分」を考える。
に関する積分」を考える。
各 ![]() は
は ![]() であるので、
この範囲を確率測度空間にするために
であるので、
この範囲を確率測度空間にするために
![]() , すなわち
, すなわち
まずは、![]() の評価を考える。
の評価を考える。
(7.105)
また、![]() を
を ![]() で積分すると、
で積分すると、
(7.109)
(7.110)
自然数 ![]() を、
を、
![]() なるものとすると
なるものとすると
![]() に対して
に対して
![]() であり、
そのような
であり、
そのような ![]() に対しては
に対しては ![]() となるので、
となるので、
(7.111)
(7.112)
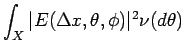 | ||||
| (7.114) | ||||
![]() のある可算部分集合列
のある可算部分集合列 ![]() があって、
任意の
があって、
任意の
![]() に対し、
ある部分列
に対し、
ある部分列
![]() が取れて次を満たす。
が取れて次を満たす。
これは、任意の連続関数がコンパクト集合上多項式で一様近似できること
(Weierstrass の定理) と、
![]() 上 1 で
上 1 で ![]() の元であるような
関数列
の元であるような
関数列
![]() を使えば容易に示せるので証明は省略する。
を使えば容易に示せるので証明は省略する。
この補題 7.1 の ![]() に対する
に対する
![]() を考えると、その和
を考えると、その和
![]() も 0 集合
(
も 0 集合
(![]() ) であり、
一方部分列の方は、この
) であり、
一方部分列の方は、この ![]() に関して次のような部分列の列を作る:
に関して次のような部分列の列を作る:
(7.115)
このとき、任意の
![]() に対して、
補題 7.1 の
に対して、
補題 7.1 の
![]() と
と ![]() ,
, ![]() を取れば、(7.8) により、
を取れば、(7.8) により、
この
![]() に対し、
6 節の議論を用いてある
に対し、
6 節の議論を用いてある ![]() に収束する部分列
に収束する部分列
![]() を取れば、
を取れば、
![]() に対してはその極限
に対してはその極限 ![]() が
弱解になることが言えたことになる。
が
弱解になることが言えたことになる。
竹野茂治@新潟工科大学